【インターンインタビュー】インターンシップの私がバイデンハウスで経験したこと -やり遂げる力

プロフィール
菊田 祐太郎 (21歳) |株式会社バイデンハウス インターンシップ
帝京大学 経済学部 経営学科
Internship, Weiden Haus
菊田です。 中高一貫の進学校に通っていました。現在は、比較制度分析、計量経済学を中心にミクロ、マクロを問わず幅広く勉強をしています。2025年秋からフィリピンへ留学予定です。また、2026年春から同大学院に進学すると共にラオスに留学する予定です。MBTIはENTPです。
ほかのインターン会社やアルバイトは?
大手ECサイト運営企業様と共同で、購買データを用いた販促施策の検証や、ペルソナ作成のための消費者分析をマーケターやデータアナリストの方々と行った経験はありました。しかし、インターンやアルバイトといった経験はありませんでした。
将来目指していることや夢
将来は国際機関や政府シンクタンクのリサーチ系で働きたいと考えています。
バイデンハウスとの出会い
なぜバイデンハウスへ?
大学の後輩から石崎さん(社長)の話を聞いたことがきっかけでバイデンハウスを知りました。そのときはインターンをすること自体全く考えていませんでした。大学の先輩がマーケティング系のインターンを探していたので、私も一緒にインターンの面談について行きました。
面談で石崎さんと三上さん(取締役)にお会いし、年齢が近いのに大手企業を相手にしていることにまず驚きました。さらに、Z世代や消費者と真剣に向き合う姿勢が印象的で、「自分にはない視点を持っている」と強く感じました。実際にPCを使いこなす姿を見て、仕事のスピード感やプロフェッショナリズムを体感し、「この人たちと一緒に働きたい」「この環境なら成長できる」と思いました。
その結果、採用されたのは先輩ではなく僕自身で、まさかの展開ではありましたが、これも一つの縁だと思い、挑戦を決意しました。
実際のインターンシップ体験
バイデンハウスで実際にどのような業務を担当しましたか?
最初の業務は、コンサルタントの方々のアシスタントでした。そこでは、資料作成やリサーチ業務などを担当し、業務の流れを学びました。 その後、消費財のマーケティング支援のプロジェクトで生活者の行動分析や市場調査をメインに行いました。
そこから、一連の分析業務の経験を活かして、生成AIを社内のリサーチ業務に導入しました。バイデンハウスの分析業務の効率化を実現しました。5営業日かかりそうな分析を1営業日でできるくらいの効果がありました。
他には以下のタスクフォースに参加し、私がリーダーとしてプロジェクトを推進しました。
通常であれば複数人で分担されるような多岐にわたる業務を、ほぼ一人で担当しました。
- 事業に必要な国家資格の取得・官公庁案件への入札
- マーケティングリサーチ専門子会社の設立
- バイデンハウスのマーケティング組織の立ち上げ
- CRM(顧客管理システム)導入
業務を通じて学んだこと、気づいたこと
プロフェッショナルとして働くにあたり、日本語やコミュニケーションの難しさに直面しています。バイデンハウスでは、必要最小限の文章で相手に理解させ、行動を促せるような伝え方が求められます。とくに、「主題→結論→理由」で話すような結論ファーストの話し方は、常に時間が限られる中で戦力になるために意識的に矯正しました。
難しかったこと、どうやって乗り越えましたか?
情報を自分で積極的に収集し、プロジェクトを前進させるのが大変でした。
社長からの無茶難題のようなミッションに応える仕事が多く、そのほとんどが社内にはない知識であるため、自分から知識を取りに行く必要がありました。 マーケティング組織立ち上げの際は、システムを導入する必要があり、400ページぐらいの専門書を社長に買ってもらいました。 それを自分で読んで、実際に手を動かし、試行錯誤を繰り返しました。
また、「今、自分が何がわからないのか?」「何がわかれば自分は進めるのか?」を都度定義することが難しかったです。自分がわからないことを一通り書き並べて、生成AIを活用しながら疑問を整理しまして。GoogleやChatGPTでわかることと、社内で質問するべきこと、社外に問い合わせることを区別しながら一つ一つ潰していきました。官公庁の案件など、正確性が求められる業務では行政が提示している手引書などで確認しながら進めることで、一つずつ不安を解消しながら取り組みました。
特に楽しかった業務、達成感を感じた瞬間
シャンプーの案件で、訪日外国人むけの売上の成長戦略を考える、という案件を担当しました。外国人観光客の購買データを分析したときに傾向が見えてきた時が楽しかったです。大学の研究の感覚だと、1000人ぐらいのデータが必要だと思っていましたが、実務的には200人ぐらいのデータでこんだけ明確に傾向が見えるのかという驚きがありました。
また、国家資格を取ったり、生成AIやシステムを社内導入して形になって、社内で使われるようになった瞬間に達成感を感じました。私一人でやり切ったことが社内に広がっていく瞬間があり、日に日にじわじわと達成感を感じました。
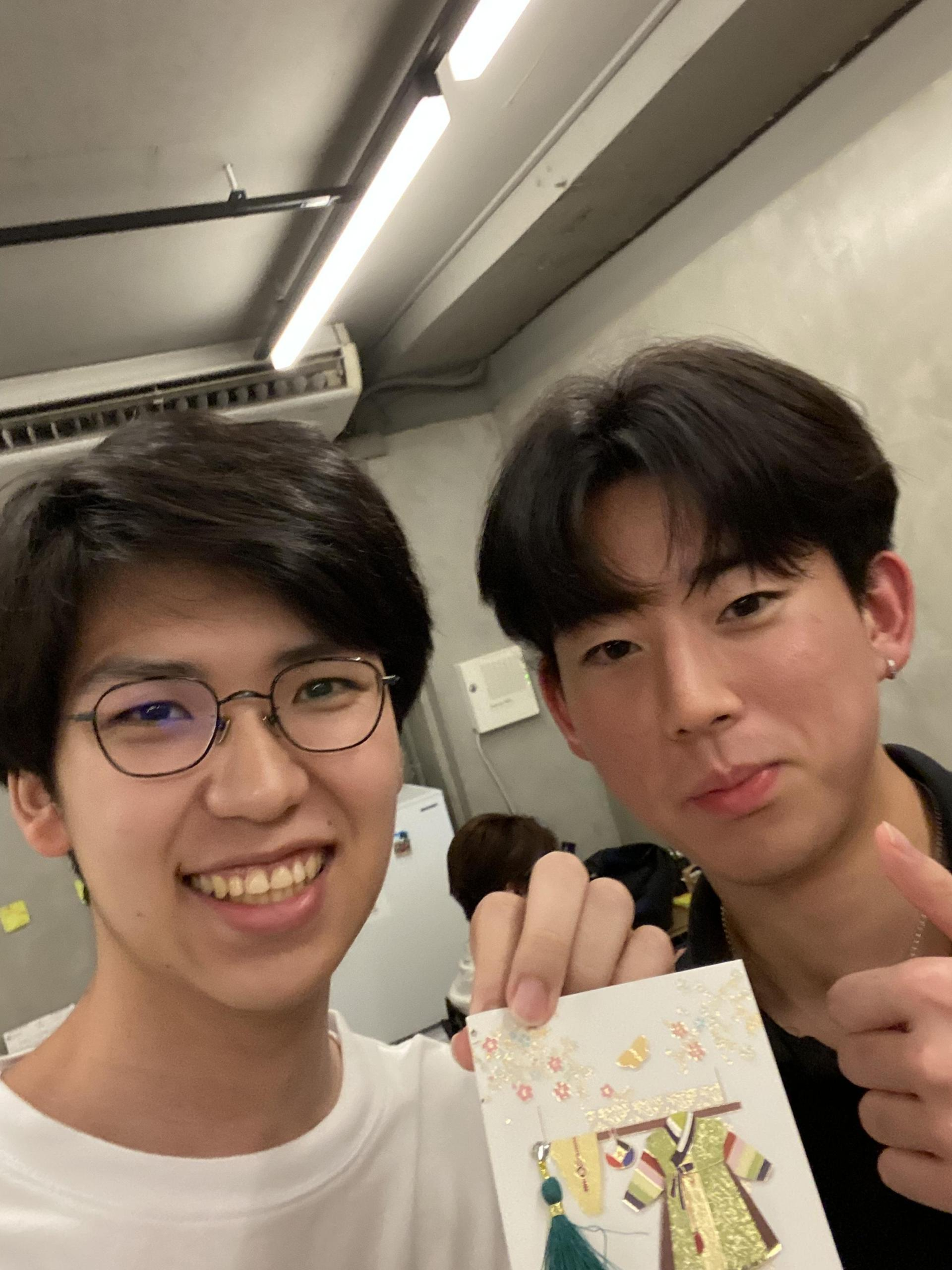
写真:アメリカからバイデンハウスにインターンに来たRayの送別会
「仕事って面白い」と思った瞬間は?
予想もできない経験が、後になって思いがけず活きる瞬間に「仕事って面白い」と感じます。
たとえば、ある夜中にコロナで寝込んでいたとき、社長から突然「官公庁の入札案件をやらないか」とLINEがありました。
深夜2時、熱にうなされながら「やります」と返事をしたのですが、そこから慣れない行政手続きとの格闘が始まりました。 法務局の港出張所を探して麻布十番をうろうろしたり、印鑑証明カードを忘れて手続きが進まなかったり、三田の税務署に行ったら窓口が違うといわれ、結局麻布の税務署まで足を運ぶなど、書類の申請・提出・受け取りを何度も繰り返しながら、なんとか国の資格を取得することができました。
資格を取得したのも束の間、今度は社長に「子会社を作って」と任されました。
「え、インターン生の僕が子会社を作るの…?そんなことまでやらされるのか!」と心の中で何度も叫びました。
会社の倉庫から資料を掘り出し、山積みの行政書類に囲まれ、法務局や税務署を駆け回り、印鑑証明や申請書類の細かい不備で何度もやり直し。「1ヶ月で子会社を作る」というスピード感の中、平日は一日10時間、朝から夜までフル稼働する日々が続きました。行政機関の閉庁時間に合わせて、時間との戦いもありました。
それでも少しずつ「やればなんとかなる」という感覚を掴み、資格で得た知識をフル活用して書類提出や登記手続きを着実に完了させました。
後にシステム導入のような複雑な業務にも、恐れず挑戦できる自信につながりました。今では、目をつぶって港出張所や麻布の税務署の窓口に行けるほどで、港区出張所の窓口のおじさんに顔を覚えられたくらいです。振り返れば、深夜のLINE一通から始まった想像を超える予想外の挑戦が、自分の成長の大きな糧になっています。
会社やチームのカルチャー
バイデンハウスの雰囲気
この会社の雰囲気を一言で表すと「自由で熱量が高い」です。オフィス内での見た目や働き方も自由で、社員それぞれが自分に合ったスタイルで働いています。議論が飛び交い、意見やアイデアが自由に交換されるので、個々の価値観や強みを形にしやすい環境だと思います。
クライアントファーストの姿勢が徹底されており、常に時間に追われる緊張感の中で臨機応変に対応する必要があります。自由さの中にも、成果を出すための熱量やプロフェッショナルとしての鋭さがあり、挑戦意欲を刺激される雰囲気が常にあります。
メンバーとの上下関係
特に年齢や上下関係を意識することはほとんどありません。PMの方がプロジェクト全体を管理していて、必要なときにはフィードバックをいただきますが、指示や命令というより「こうするともっと良くなるよ」と気さくに教えてくれる感じです。
年齢も近く、社員も10人ほどの少人数なので、困ったことや相談ごとも気軽に話せます。好きな芸能人のライブに行った話やカルチャーやトレンドの話など、雑談が良く飛び交っていて、フラットで温かい空気があります。

写真:チームで神輿を担ぎました
成長や変化の実感
インターン前と後で変わったこと
「Why」を常に意識するようになりました。社長が外資系コンサル出身ということもあり、問いかけの仕方が非常にロジカルで、日々「なぜ?」「それは何を意味する?」「どうやる?」を突きつけられます。クライアントも同じように考える方が多く、その影響で自然と自分も論理の筋道を意識する癖が身につきました。以前は「言われたことをやる」感覚が強かったのですが、今は「なぜそれをやるのか」をまず考えてから動くようになりました。
行動面では、主体性が大きく変わりました。まずは自分で調べてトライし、分からなければAIを使い、それでも解決できなければ上長に相談する、という順番を徹底しました。結果として、なるべく自分で完結できるよう努めつつ、他の人が同じ道筋を追えるようにプロセスをきちんとまとめる意識が強くなりました。「自分がやった仕事を、他の人が再現できるようにする」という視点を持てたのは、インターンを通じた大きな成長だと感じています。
あとは、手さばきが早くなりました。(笑)
タイピングが目に見えて向上しました。大学に入ってからPCを使い始めたので、インターン前の大学2年生当時は「寿司打」で高級コースに挑んでも3,000円程度しか残せませんでした。今ではブラインドタッチに慣れ、+5,000円以上の“おつり”が出るようになり、「e-typing」でも常にGood!を取れるレベルです。
また、エクセルやパワーポイントの作業スピードは格段に上がりました。業務の中でショートカットキーを必須で覚えないと仕事が回らない環境だったので、単純に早くなっただけでなく、「仕事を効率的に進める武器」として実感できるようになりました。
「これを経験できてよかった」と思うこと
私にとって大きかったのは、社内と社外の両方で異なる成長機会を得られたことです。
社内では、様々なプロジェクトを通じて、「バイデンハウスに役に立つにはどうすればよいか」「実現のためにどんな手順が必要か」を常に意識するようになりました。与えられた仕事をこなすだけではなく、自分のアウトプットが組織全体にどう影響するかを考える視点が身についたのは、大きな収穫でした。
一方で社外では、普段出会うことのないマーケターのクライアントと対峙し、支援する経験ができました。クライアントの方の立場・状況によって求められるスタイルを変えながら成果を出す難しさと楽しさを学び、「相手の立場に立って考える」ことの重要性を肌で実感しました。
社内外の両方で挑戦できたことは、自分の視野を広げるだけでなく、「内向きに仕組みを作る力」と「外向きに相手と協働する力」の両輪を鍛える機会になり、これを経験できたことを心からよかったと感じています。
読者へのメッセージ
これからインターンを考えている学生へのアドバイス
多くの人は「エントリーシートに書ける経験を作ろう」とか「志望業界に近い経験を積もう」と考えてインターンを探すと思います。もちろんそれも大切だと思いますが、私が実際にやって良かったのは、あえて自分の関心から少し外れた業界に飛び込んでみたことでした。
私自身、バイデンハウスでインターンを始める前は、マーケティングやコンサルティングについて、大学の講義や本で聞いた程度の知識しかありませんでした。共同研究を通じて多少の理解はあったものの、実務的な調査の手法などはほとんど分かっていませんでした。
実際にインターンとして業務に取り組んでみると、全く知らなかった業界のクライアントと向き合うことになり、「世の中にはこんな考え方や文化があるのか」と驚く発見が数多くありました。その経験を通じて、自分の興味の外にこそ大きな学びが隠れているのだと気づきました。 だからこそ、「志望業界に絞らなければ」と焦るよりも、少し自分の枠外にある業界に挑戦してみるのも価値があると思います。思いがけない経験が後に役立つこともありますし、何より「仕事は面白い」と感じられるきっかけになると思います。
バイデンハウスに向いている人は?
バイデンハウスでは、用意された正解を答えるのではなく、場を揺さぶり、新しい切り口を提案することが求められます。 私自身、人見知りで、万人受けするような人当たりの良さはありません。話し方も早口です。それでも、自分なりに理屈をもって意見を述べ、好奇心を原動力に考えを深め、議論に加わっていました。その積み重ねが評価され、次第にさまざまな役割を任せてもらえるようになったと考えています。正解のない課題に向き合うなかで、「考え抜く」「まずやってみる」という泥臭い姿勢が、自分の中に確かに根づいたと感じています。
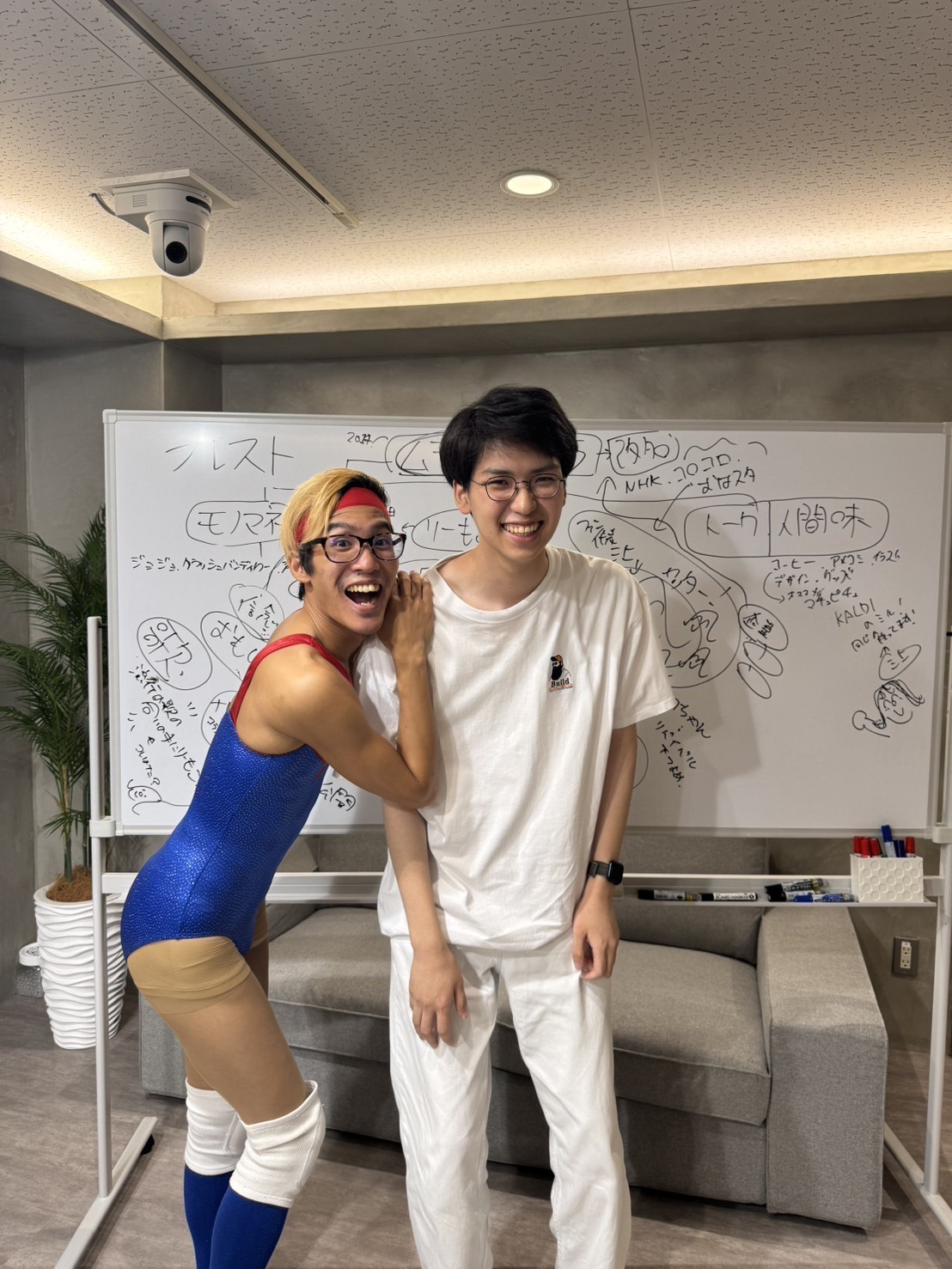
写真:バイデンハウスの皆さんとお笑い芸人のムラムラタムラさんの企画に参加しました。



